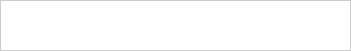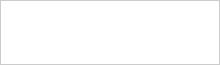→月刊「地方議会人」最新号詳細はこちら
→月刊「地方議会人」最新号詳細はこちら
A4判 68ページ 年間購読:9,972円/単月号:831円(税・送料込み)
「月刊 地方議会人」デジタルブックサンプル版はじめました!
「月刊 地方議会人」サンプル版ではデジタルブックで地方議会議員・議会事務局の方々に好評の特集、現地報告2本、連載2本を「無料」で読むことができます!
デジタルブックでのサンプル版となるため、「ワード検索」などにも対応していますので、ぜひご覧になってみてください。
→デジタルブックサンプル版の閲覧はこちら、もしくは左側の画像をクリック!
「月刊 地方議会人」デジタルブックサンプル版 概要
1) 特集
地方議員の政策づくり、6つの戦略 「政策に強い議員」 をめざそう/礒崎初仁(中央大学副学長)
2) 現地報告
岩手県奥州市 民意実現のためにスピード重視の政策へ 当局計画への施策取り込み作戦
/菅原由和(岩手県奥州市議会議長)
長野県宮田村 宮田村むらづくり基本条例に基づき持続的な議会改革を
/天野早人(長野県宮田村議会議長)
3) 連載(議会運営講座)
一般質問パワーアップ・ブック いかに政策に結びつけるか/牛山久仁彦(明治大学政治経済学部教授)
4) 連載(広報・研修資料)
議会広報紙を見やすく、わかりやすく/吉村 潔(エディター・広報アナリスト)
月刊「地方議会人」とは…
① 地方議会・地方自治をテーマに多彩な特集や現地事例を解説
各年の特集バックナンバー詳細はこちらをクリックください
② 議会の手引書となる様々な連載
教養講座 議会のデジタル化をはじめてみよう!
長内紳悟(一般社団法人地方公共団体政策支援機構 代表)
市町村議会においてデジタル化が多様な広がりを見せています。さまざまなデジタル端末やシステムを活用して、住民に開かれた議会を実現するための基本中の基本をわかりやすく解説。
議員研修講座 シリーズ 女性議員はどうすれば増えるのか
日本の女性議員の現状はどうなってるの?女性議員を取り巻く困難について(ハラスメント、産休・育休)や、女性議員が思うように増えていない地方議会のいま…について多彩な執筆陣により、わかりやすく解説。
地方議会最前線 ―「開かれた議会」を創る(リレー連載)
市町村議会の政策活動に結びつくアドバイスをしている議会アドバイザーや有識者が、担当する議会の先進事例や特色を深掘りして解説。
職員研修講座 地方議会事務局 Q&A 議員をサポートする秘訣を教えます
吉田利宏(議会事務局実務研究会 議会アドバイザー)
地方議会事務局職員にとって必ず知っておきたいこと、議員と事務局の役割分担、作法と心得、情報収集の方法など、議会事務局職員にとって必須のポイントをQ&A 形式でわかりやすく解説。
シリーズ 随想 地方議会について考えたこと
毎月違う著者よるによる新シリーズ「随想 地方議会について考えたこと」が始まりました。様々な著者が月毎に違うテーマで 地方議会への想いを語る随想です。
③ わかりやすい議会広報の作り方を紹介
議会広報紙を見やすく、わかりやすく
評者 芳野政明、吉村 潔、長岡光弘、前田安正、金井茂樹、佐久間智之(テーマ別リレー連載)
市町村議会の議会広報紙を掲載し、「住民に読まれる議会だよりとは」、「表紙デザイン」、「見出し対応」、「一般質問」、「予算・決算」、「デジタル対応」、「SNS・ネット・タブレット対応」などのテーマ別に各専門講師が誌上広報研修を掲載。
④ 全国市議会議長会、全国町村議会議長会の活動を紹介
議長会ニュース
全国市議会議長会、全国町村議会議長会